参考書レビュー
2025年1月7日
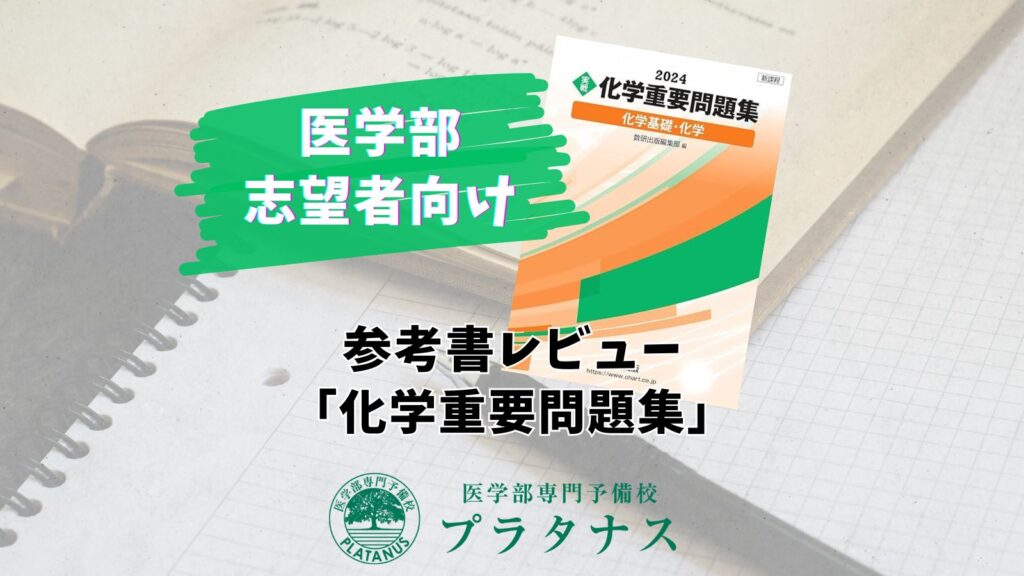
医学部専門予備校プラタナスです。プラタナスでは生物選択者の私立医学部進学に特化した参考書レビューを行なっていきます。今回取り上げる参考書は「化学重要問題集 化学基礎・化学」です!特に浪人生に向けた使い方などを提案しますので、ぜひ参考にしてください。
医学部受験において、化学は非常に重要な科目のひとつです。英語・数学に加えて、理科の科目は得点源にしやすい傾向がありますが、特に化学は「論理的思考力」と「正確な知識」が要求されるため、徹底した演習量と深い理解が求められます。一年という限られた浪人生活の中で、効率よく化学の実力を伸ばすには、演習・復習を繰り返せる良質な参考書を厳選し、計画的に取り組むことが必要不可欠です。
今回ご紹介する「化学重要問題集 化学基礎・化学」(以下「重要問題集」と呼称)は、多くの受験生・浪人生から支持されている定番の演習書で、医学部受験対策としてもおすすめです。本記事では、浪人生をターゲットにした医学部専門予備校の視点から、「重要問題集」を用いた学習方法や、使い方のコツを具体的に解説していきます。大学の医学部進学を目指す浪人生にとって、参考書選びは勝負を分ける大きな要素です。ぜひ最後までお読みいただき、自分に合ったスタディプランを立てる際のヒントにしていただければと思います。
参考書の基本情報と特徴
著者・出版社・定価
• 著者: 数研出版編集部
• 出版社: 数研出版
• 定価: 935円(税込)(学校採用専用書籍のため解説は別売り)
本書「化学重要問題集 化学基礎・化学」は、高校化学や大学受験化学を扱う参考書で知られる数研出版から刊行されています。数研出版は、数学や理科の参考書で名高く、特に「体系的に学べる」構成と「問題演習を重視した」編集で有名です。
レベル・どのレベル(段階)の人におすすめか
「重要問題集」は高校化学の学習を一通り終えており、基礎事項は把握していて、ある程度演習に慣れてきた人におすすめの参考書です。浪人生の方の場合、すでに一度受験を経験している分、全くの初心者という方は少ないかと思いますが、
• 化学基礎・化学の基本教科書レベルは概ね理解している
• ある程度の演習経験もある
という人にとって、よりハイレベルな問題演習をこなしながら、抜けやすいポイントを再確認するのに役立ちます。医学部受験ではハイレベルな問題にも挑む必要があり、「重要問題集」レベルの演習は必須と言えるでしょう。
メリット
1. 問題数が豊富で網羅性が高い
化学基礎・化学の頻出分野を網羅しており、漏れなく演習ができます。標準問題から応用問題まで、厳選された良問が揃っているため、総合的な力が養われます。
2. 解説が丁寧でポイントを押さえている
各問題に対して、必要となる知識や考え方がきちんと説明されており、解説を読み込むことで応用力が身につきやすいです。
3. 医学部レベルの難易度への対応が可能
難関大学や医学部向けの高難度問題も収録されているため、高い目標を持つ浪人生にとって実戦的な演習ができます。
4. 基礎から応用まで階段状に学べる
前半では比較的基礎的な問題、後半ではやや発展的な問題が配置されており、段階的に力を伸ばしていく構成となっています。
デメリット
1. 解説がコンパクトにまとまっているがゆえに、理解に時間がかかる場合がある
ポイントを押さえた解説ではありますが、化学の背景知識や深掘りした解説を必要とする場合は、別の参考書を併用するとさらに理解が深まります。学校用の教材ということもあり、別冊解答が学校で配られるなど、入手の可否によって使いやすさが異なります。
2. 問題数が多く、全範囲をきちんとこなすには時間がかかる
浪人生は一年で結果を出す必要があるため、計画的に学習を進めないと途中で手が回らなくなる可能性があります。
内容の特徴と具体的な使い方
内容と特徴
「重要問題集」は、以下のような特徴的な構成になっています。
• 章立ては教科書の流れに沿っており、化学基礎から無機・有機・理論まで体系的
化学基礎・化学全範囲を網羅しており、抜け漏れを最小限に抑えられます。大学入試で頻出の分野や問題形式を重点的に取り上げているので、効率よく対策が可能です。
• 演習を通じて、教科書レベルの知識を定着させながら実戦力を高められる
医学部入試では深い理解力や応用力が問われるため、丁寧に問題を解いていく中で「なぜこの解法が成り立つのか」「公式や概念をどのように応用するか」などを常に意識することが求められます。
• 標準問題から発展問題まで一貫して習得可能
単に難易度の高い問題が羅列されているのではなく、標準~発展まで順序立てて並んでいるので、自身の到達度に合わせてステップアップできます。
具体的な使用方法
学習スケジュールの例
本書を効果的に使うためには、やみくもに問題を解くだけではなく、1周目は知識の確認と基礎固め、2周目は解法の習得と応用力強化、3周目は演習速度の向上と総仕上げというように段階を踏んだ繰り返し学習がおすすめです。
1. 1周目
• 分野ごとの基礎事項を確認しつつ、各問題を丁寧に解いてみる。
• 解説を読み込みながら公式や知識の抜け漏れを洗い出し、ノートなどにまとめる。
• この段階でペースを乱しすぎず、分からない問題はある程度割り切って解説をしっかり読むのが大事。
2. 2周目
• 1周目で分からなかった問題や間違えた問題を中心に再挑戦。
• “なぜ間違えたのか?”を明確にし、理解の定着を図る。
• 計算問題なら式変形のプロセスを再確認し、反応機構や反応経路が理解できていない場合は関連分野の基礎書に立ち返る。
3. 3周目
• 本番レベルの時間配分を意識して、実践感覚で演習。
• 医学部の過去問を併用して、本書の類題が出たら確実に解けるかをチェック。
• 得意分野はスピードアップ、苦手分野はじっくり解説を再確認し、最終的な穴埋めを行う。
習得までの分量と目安時間
• 「重要問題集」は分野別に問題が充実しているため、全範囲を2〜3周するのに約2〜3か月程度を見込むと良いでしょう。
• 1日の演習時間としては、他科目との兼ね合いもありますが、まずは1日に1〜2単元(約10〜20題程度)を目安に取り組むことをおすすめします。
• 医学部受験を狙うなら、英語・数学などの重点科目とのバランスを考慮しつつ、「重要問題集」には必ず時間を割くよう心がけてください。
浪人生活の時期別の使い方
浪人生にとって、限られた1年をどう配分して学習を進めるかは非常に重要です。ここでは、受験期初期(4〜6月頃)、夏休み中(7〜8月頃)、秋~直前期(9月以降)という3つの時期に分けて、「重要問題集」の使い方を提案します。
受験期初期(4〜6月頃)
• 目標: 基礎固め+標準レベル問題の網羅
• 学習のポイント:
1. 「重要問題集」の最初の方にある基礎的な問題から取り組み、化学基礎の抜け漏れをチェック。
2. 早めの段階で、苦手分野を明確化しておき、必要に応じて別の基礎参考書や問題集に戻りながら理解を深める。
3. 無機化学や有機化学など暗記事項が多い領域も、この時期から分割してコツコツ進める。
夏休み中(7〜8月頃)
• 目標: 標準レベル問題の定着+やや難易度の高い問題へのチャレンジ
• 学習のポイント:
1. 受験期初期における1周目を終了し、2周目の復習を行う。間違えた問題を重点的に解き直す。
2. 個人的に弱い分野を集中強化。例えば、有機化学の構造決定問題や理論化学の計算分野など、医学部入試の頻出テーマに重点を置く。
3. スキマ時間を活用して、暗記事項の整理や化学反応式の再確認を行う。
秋~直前期(9月以降)
• 目標: 応用力・演習速度の強化+総合力の仕上げ
• 学習のポイント:
1. 2周目・3周目を通じ、苦手分野を徹底的につぶす。
2. 医学部の過去問演習と平行して、「重要問題集」の発展問題に再挑戦。解答時間を意識しつつ、本番での得点力を高める。
3. 最終的に、“ここに戻っておけば安心”というノートや解説まとめを作り、入試直前まで繰り返し確認する。
つまずいたときに戻るとよい参考書・クリア後に進むとよい参考書
つまずいたときに戻るとよい参考書
• 数研出版「リードLightノート 化学基礎・化学」
「リードLightノート」は、教科書準拠で要点が整理されており、基礎事項を確認するには最適です。計算問題や反応式など、難しい単元に行き詰まったときには、まず「リードLightノート」で基本的な考え方や定義を再チェックしましょう。
使い方:
1. 「重要問題集」で解けなかった問題の分野に対応するページを開く
2. 基本事項を再インプットし、理解不十分な計算式や反応原理を確認
3. もう一度「重要問題集」の該当問題に取り組み、解説を読み直す
• 鎌田真彰「化学 基礎問題精講」(旺文社)
「基礎問題精講」は、問題量が比較的コンパクトな構成で、ポイントを押さえやすいのが特徴です。テーマごとに例題→問題という流れになっており、抜けがちな要点を再確認する際に役立ちます。
使い方:
1. 弱点分野ごとの例題から解き直し、基本的な解法を頭に入れる
2. その後、類題で演習することで定着を図る
クリアしたら進むとよい参考書
• 三省堂「大学入試 理系化学の新研究」
「新研究」は知識の網羅性が高く、かなり詳しい理論解説がまとまっています。医学部入試の中でも難易度の高い大学を目指すのであれば、反応機構や無機・有機の複雑な分野をしっかり理解するためにも、より深い内容を扱う参考書が必要です。
使い方:
1. 「重要問題集」で把握した苦手分野や、さらに深掘りが必要な内容を中心に読む
2. 専門的な知識や反応機構の詳細をインプットし、演習を通じて出題パターンを把握
• 数研出版「重要問題演習 化学」上級レベルの問題集
もし「重要問題集」の内容をスムーズに習得できたら、次はさらに上級レベルの問題集に手を伸ばすのも良いでしょう。大学入試本番で差がつく問題や、医学部独特の出題形式を扱う演習書に触れることで、一段上の得点力を養成できます。
使い方:
1. 医学部の過去問に近い形式の問題を中心に演習
2. 解説を読んでも分からない部分は、必要に応じて「新研究」などに戻って理論を確認
医学部受験に役立つ「重要問題集」の活用ポイント
ここでは、「重要問題集」を使って医学部受験特有の要件を満たすための、より具体的な学習ポイントをまとめます。
1. 計算問題を徹底的に訓練する
医学部の化学入試では、理論化学の計算力が合否を分けることが多いです。酸化還元滴定や中和滴定、気体の法則など、頻出かつ計算量の多い分野を特に重点的に取り組みましょう。問題演習→解説の読み込み→再演習を繰り返すことで、計算ミスの防止とスピードアップを図ります。
2. 無機・有機の暗記事項をスキマ時間でこまめに確認
無機化学と有機化学は、反応の特徴や色、沈殿など細かい暗記事項が多く、後回しにしがちです。しかし、医学部を目指すうえでは、暗記事項を正確に覚えているかどうかで差がつきます。移動時間や休憩時間を活用して、こまめに整理ノートを復習するのがおすすめです。
3. 過去問とリンクさせて利用する
「重要問題集」で扱った問題パターンが、実際の医学部過去問でどのように出題されているかを確認しましょう。定量的に捉えることで、時間配分や出題形式への慣れを養うことができます。
4. 他科目(英語・数学・物理・生物)とのバランスを意識する
浪人生にとって、一年で全科目の完成度を高める必要があります。化学に偏りすぎず、他の理科科目や英語・数学とのバランスを取りつつ、計画的に「重要問題集」を進めることが大切です。
まとめ
最後に、本記事のポイントを振り返りつつ、「化学重要問題集 化学基礎・化学」を活用して医学部合格を目指す浪人生の皆さんへメッセージをお伝えいたします。
• 「重要問題集」は基礎から応用まで一貫して学べる良質な問題集であり、医学部レベルにも対応できる優れた参考書。
• 演習の量は多いが、丁寧で体系的な解説があるため、浪人生が抱えがちな化学の弱点を網羅的に補強できる。
• 医学部合格に必要なのは、“深い理解”と“正確な演習量”。一度理解した内容を忘れないように、繰り返し解き直すことが最も大切。
• 計算問題や有機・無機分野に苦手意識を持つ場合は、必ず他の基礎参考書に戻って復習する。また、余裕があれば「新研究」のような上位参考書や、医学部過去問でより深いレベルの演習に取り組む。
• 浪人生の一年はあっという間。計画的に学習スケジュールを組み、“この期間にここまでやる”と明確な目標を設定して取り組むことが鍵となる。
受験勉強は決して楽な道のりではありませんが、日々の努力が医学部合格へと確実に近づく道しるべとなります。自分を信じ、焦らず着実に、「化学重要問題集 化学基礎・化学」で力をつけていきましょう。応援しています。
医学部専門予備校プラタナスへのお問い合わせ
その他入塾やご質問事項に関しては。「お問い合わせ」または「LINE無料相談」からお気軽にご連絡ください。
面談はリモートでも受け付けております。
• 参考書名: 化学重要問題集 化学基礎・化学
• 参考URL: https://www.amazon.co.jp/新課程-2024-実戦-化学重要問題集-化学基礎・化学/dp/4410143344

無料LINE相談
随時受付中
無料
体験・相談
お申し込み


 アクセス
アクセス
