解答速報/入試分析
2025年1月23日
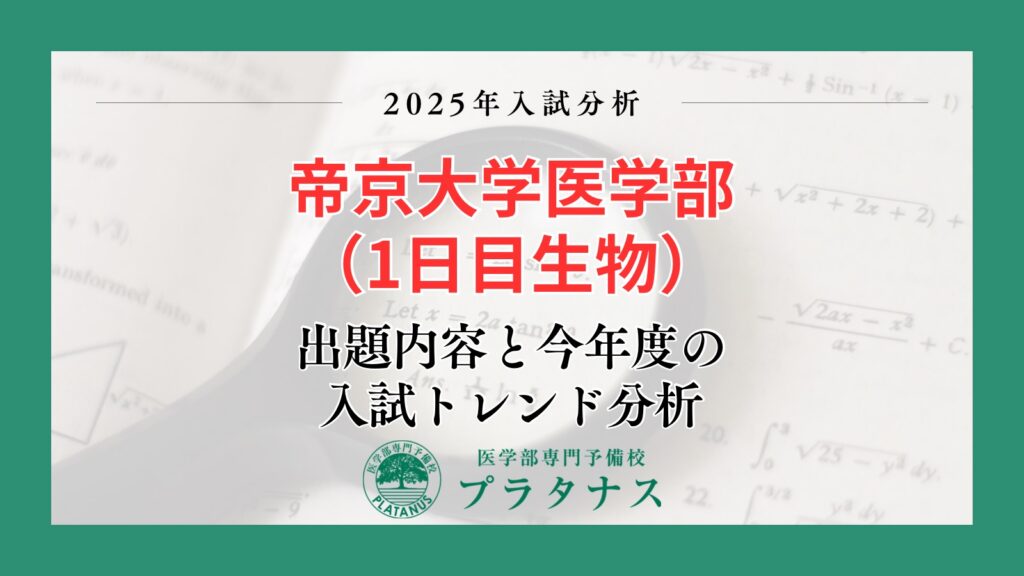
私立医学部専門予備校のプラタナスです。
本日は,帝京大学(1日目)と杏林大学の試験でした。
皆さん,お疲れ様でした!杏林大学の解答速報はまた別に出すのでお待ちください。
やはり,帝京大学は「体内環境」の出題率が高かったですね。
明日の予想は一番最後に書いたのでご覧ください。
出題内容
1:体内環境(ホルモン)
→リンパ液,ホルモンの定義(記述),ホルモンの特徴,受容体(ステロイド系とペプチド系),体温を上げるホルモン,
2:代謝(呼吸)・植物ホルモン
→電子伝達系,H+の移動(記述),ATPの構造,ATPの合成数(計算問題)
→植物ホルモン,種子の発芽,肥大(エチレン)
3:体内環境(免疫)
→リゾチームの働き(記述),花粉症,マスト細胞,アナフィラキシー,サイトカイン,抗原決定基の考察問題
■解糖系
反応場所は細胞質基質でグルコース1分子あたり差し引き2ATPを産生している。
(2ATP消費し,4ATP産生)
10種類の酵素の働きにより進行し,脱水素酵素などにより1分子のグルコースから2分子のピルビン酸ができる。
C6H12O6+2NAD+→2C3H4O3+2(NADH+H+)+2ATP
■クエン酸回路
反応場所はミトコンドリアのマトリックスで行われ,グルコース1分子あたり2ATPを産生する。解糖系で生じたピルビン酸が,脱炭酸反応と脱水素酵素により完全に分解される。
2C3H4O3+6H2O+8NAD++2FAD→6CO2+8(NADH+H+)+2FADH2+2ATP
物質は変化していき,
ピルビン酸→アセチルCoA(+オキサロ酢酸)→クエン酸→αケトグルタル酸→コハク酸→フマル酸→リンゴ酸→オキサロ酢酸
覚え方は「クエンさん(クエン酸),急いで蹴とばし(αケトグルタル酸)怖くなり(コハク酸),踏まれた(フマル酸)リンゴ(リンゴ酸)を置き去りに(オキサロ酢酸)」
■電子伝達系
ミトコンドリアの内膜で行われNADHやFADH2から放出された電子が電子伝達系を通る。
これに伴って,H+がマトリックス側から膜間腔に輸送される。
電子は最終的にH+やO2とともに水が生成される。
膜間腔からマトリックスへATP合成酵素を通る時に多くのATPが生成される。
■植物ホルモン
| 【植物の生い立ち】 | 植物ホルモン | 光受容体 |
|---|---|---|
| ①種子の発芽 | ジベレリン(促進:休眠打破) アブシシン酸(抑制:休眠維持) | フィトクロム |
| ②成長 (伸長成長) | ジベレリン,ブラシノステロイド,オーキシン (縦に伸長) | フィトクロム クリプトクロム |
| ③成長 (肥大成長) | エチレン,オーキシン (横に肥大) | |
| ④成長 (屈性) | オーキシン | フォトトロピン |
| ⑤成長 (頂芽優勢) | オーキシン(側芽の成長抑制) サイトカイニン(側芽の成長促進) | |
| ⑥花芽形成 | フロリゲン ジベレリン(低温処理はジベレリン処理に代替が可能) | フィトクロム クリプトクロム |
| ⑦果実の形成 (結実) | ジベレリン(種なしブドウの作成) オーキシン | |
| ⑧果実の成熟 | エチレン | |
| ⑨葉の老化 | アブシシン酸,エチレン,ジャスモン酸(促進) サイトカイニン(抑制) | |
| ⑩落葉・落果 | エチレン(促進) オーキシン,ブラシノステロイド(抑制) | |
| ⑪蒸散 (気孔の開閉) | アブシシン酸(閉) | フォトトロピン(開) |
| ⑫ストレス応答 | アブシシン酸,エチレン ジャスモン酸 |
| 【光受容体】 | 吸収光 | はたらき |
|---|---|---|
| フィトクロム | 赤色光 遠赤色光 | ①光発芽種子の発芽 ②花芽形成 |
| クリプトクロム | 青色光 | ①花芽形成 ②胚軸伸長の抑制 |
| フォトトロピン | 青色光 | ①光屈性 ②気孔の開口 ③葉緑体の定位運動 |
■免疫と病気
・アレルギー
特定の食物や花粉などの抗原に対する免疫反応が過剰となり,生体に不利益をもたらすこと。アレルギーの原因物質はアレルゲンといい,そば,卵,花粉,ネコの毛などがある。
その結果,じんましん,ぜんそく,かゆみ,くしゃみなどの症状が生じる
・アナフィラキシーショック
アレルゲンが体内に2回目に入ったとき,特に激しい症状が現れること。
血圧低下や意識低下などの急性の強い炎症作用を起こす。ハチ毒などがある。
・花粉症
花粉が抗原として体内に入ると,B細胞で産生された抗体(IgE)がマスト細胞(肥満細胞)と結合する。このIgEに花粉が結合すると,マスト細胞からヒスタミンが放出されて,くしゃみや鼻水などの原因となる。
・エピトープ(抗原決定基)→抗原を形作る部位,実験考察問題で出題されるので言葉は覚えておこう。
■適応免疫
リンパ球を中心とした,抗原に対して特異的な反応。
体液性免疫と細胞性免疫がある。
・体液性免疫
抗体によって異物が排除される仕組み。B細胞から分化した形質細胞(抗体産生細胞)から抗体が放出される。
①抗原は樹状細胞により取り込まれ分解
②樹状細胞はヘルパーT細胞に抗原提示を行い,TCRで認識し活性化
③ヘルパーT細胞はサイトカインを放出し,その抗原をBCRで認識したB細胞を活性化
④B細胞が分化し形質細胞になる。
⑤形質細胞は抗体を産生し,抗原と結合することで抗原抗体反応をする
・細胞性免疫
抗体は関与せず,T細胞の働きで異物が排除される仕組み。
①抗原は樹状細胞により取り込まれ分解
②樹状細胞はヘルパーT細胞やキラーT細胞に抗原提示を行う。TCRで認識し,T細胞は活性化
③ヘルパーT細胞はサイトカインを放出し,マクロファージとその抗原に対応するキラーT細胞を活性化させる
④キラーT細胞は感染した細胞を攻撃し,活性化したマクロファージは活発な食作用を示す。
体液性免疫と細胞性免疫はともに,B細胞やT細胞の一部を記憶細胞として体内へ残り,二次応答のために備える。
■ホルモン
・受容体の場所
細胞内→ステロイドホルモン(性ホルモンとコルチコイド系),チロキシン
受容体は細胞内に存在し,DNAに結合して特定の遺伝子の発現を調節する。
細胞膜→ペプチド系ホルモン,アドレナリン
ホルモンが細胞膜上の受容体と結合すると,その近くにあるセカンドメッセンジャー(cAMPなど)が活性化する。そして他の酵素の活性化が起こり,特定の遺伝子の発現や酵素反応が調節される。
■体温調節
寒い時
①放熱の抑制→立毛筋の収縮・皮膚血管の収縮
②発熱の促進→代謝の促進・骨格筋の収縮(ふるえ)
暑い時
放熱の促進→発汗の促進・皮膚血管の拡張
体温上昇に関する神経やホルモン
・交感神経による立毛筋の収縮・皮膚血管の収縮
・チロキシンやアドレナリン,糖質コルチコイドによる肝臓や筋肉の代謝促進。アドレナリンは心臓の拍動の促進もしている。
・チロキシンについて
視床下部→(放出ホルモン)→脳下垂体前葉→(甲状腺刺激ホルモン)→甲状腺→チロキシン
明日の帝京大学(2日目)に向けて
昨日のブログでお伝えした通り,体内環境が1日目から多く出題された。2日目に関しても出題されることが予想されるので,「体内環境」はしっかりと確認をしておきましょう。
小問集合ですが,植物ホルモンも出題されているので「植物系」に関しても注意しておこう。
明日に向けて,「体内環境」「進化・系統」「動物の環境応答」について確認しておくと良いでしょう。明日も頑張ってきてください!
入試直前講習のお知らせ
プラタナスでは今年の私立医学部受験生に対して入試直前講習を行なっております。
参加費は無料!定員は15名です。詳しくはこちら。
医学部専門予備校プラタナスへのお問い合わせ
その他入塾やご質問事項に関しては。「お問い合わせ」または「LINE無料相談」からお気軽にご連絡ください。
面談はリモートでも受け付けております。

無料LINE相談
随時受付中
無料
体験・相談
お申し込み


 アクセス
アクセス
