解答速報/入試分析
2025年1月23日
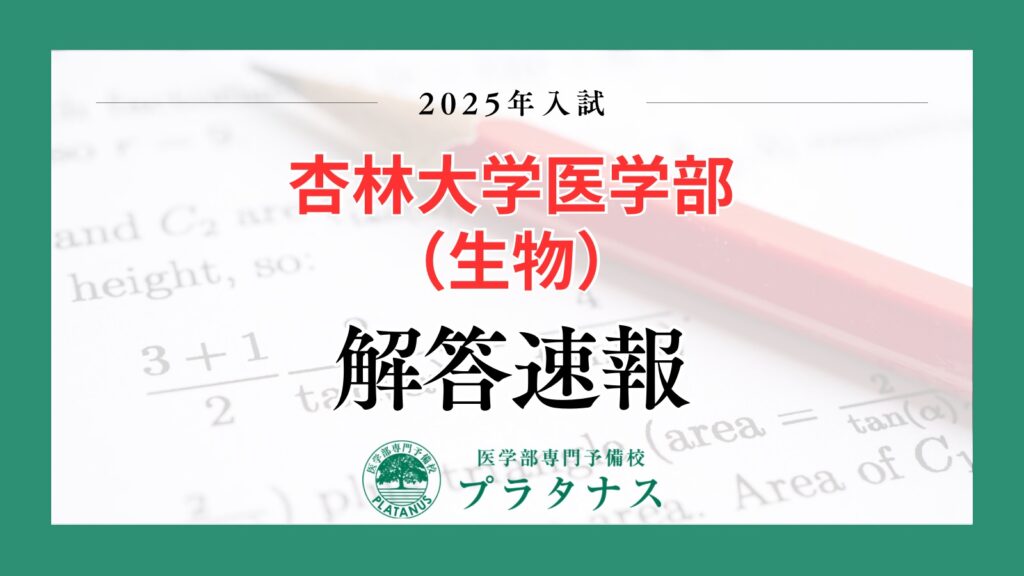
私立医学部専門予備校のプラタナスです。
本日2025年1月23日に杏林大学医学部の入試が実施されました。
以下、講評、解答、解説です。
※ミスなどを発見した場合は、お手数ですが「お問い合わせ」または「LINE無料相談」よりご連絡ください。
講評
大問数に関しては,例年通りであった。全体的に基礎から標準的な問題であった。考察問題に関しても,例年より解きやすい傾向であったと思われる。大問ⅠとⅡでどれだけ,ミスなく解けたかが鍵である。
解答
Ⅰ
問1 ① 問2 ③ 問3 ② 問4 ② 問5 ④
問6 ④ 問7 ⑤ 問8 ④ 問9 ④
Ⅱ
問1 (1) ⑤ (2) ②
問2 (1) ⓪⑧ (2) ③
問3 (1) A:① C:⑧ E:⑦ F:② G:⑥
(2) 光化学系Ⅰと光化学系Ⅱ:④ カルビン回路:⑤ (3) ⑤
(4) グルコース:⓪⑦⑤ O2:⓪⑤⑥
問4
(1) ③ (2) ④ (3) ⑤ (4) ②⑤
Ⅲ
問1 ③ 問2 ③ 問3 ② 問4 ③ 問5 ② 問6 ②
Ⅳ
問1
(1) ③ (2) ① (3) ③
問2
(1) ① (2) Vmax:③ Km:① (3) ④ (4) ②
解説
Ⅰ
問1:①
化学合成細菌を選ぶ問題である。①の亜硝酸菌である。他にも,亜硝酸菌,硝酸菌のような硝化細菌,硫黄細菌,鉄細菌,水素細菌などがあげられる。④の緑色硫黄細菌は,光合成細菌である。
問2:③
「きのこ」というキーワードで担子菌類が選べる。接合菌類は,クモノスカビとケカビという2つを覚えておこう。ツボカビ類は「鞭毛」「遊走子」「カエル」の3つのキーワードを押さえておきましょう。
問3:②
原核細胞と真核細胞の両方にあてはまるものを選ぶ問題である。①③④に関しては,原核細胞はもっていない。よって,②になる。また,アミノ酸を運ぶtRNAは原核細胞にも必要である。
問4:②
① グルコースは細胞膜を通過することはできない。GLUTやSGLTが必要である。
② 正しい。
③ グルコースは腎小体でろ過されるが,細尿管ですべて再吸収される。
④ グルカゴンではなく,インスリンである。
問5:④
バソプレシンは,間脳の視床下部にある神経分泌細胞で合成され,脳下垂体後葉から分泌される。バソプレシンの他にオキシトシンも把握しておきましょう。
問6:④
ジベレリンは,伸長成長に関与する。肥大成長を促すのはエチレンである。
問7:⑤
先体反応→卵黄膜の通過と細胞膜との融合→表層反応・受精膜の形成→卵割の順で進行する。
問8:④
① 終止コドンにより,終了するのは翻訳である。
② センス鎖ではなく,アンチセンス鎖である。
③ 5’末端ではなく,3’末端である。
④ 正しい。
問9:④
① 酸素濃度が上昇する前から化学合成細菌は出現している。
② 独立栄養の原核生物も①同様で前に出現している。
③ オゾン層が形成される前から,生命は誕生している。
④ 正しい。
Ⅱ
問1
(1):⑤
A:晩死型 例として,ニホンザルのような大型哺乳類,ハチやアリがあげられる。
B:平均型 例として,シジュウカラ,トカゲのような鳥類と爬虫類があげられる。
また,ヒドラも頻出であるので押さえておきたい。
C:早死型 例として,アサリ,イワシのような無脊椎動物と魚類があげられる。
(2):②
死亡率はグラフの傾きで判断する。よって,②である。
問2
(1) 8㎛
図2から,接眼ミクロメーターの目盛り数が5目盛りに対して,対物ミクロメーターの目盛り数が1目盛りと一致している。よって,接眼ミクロメーターの1目盛りの長さは,1×10㎛/5=2㎛である。図1から細胞Aは接眼ミクロメーターの4目盛り分に相当するので,2㎛×4=8㎛になる。
(2) ③
対物レンズの倍率が半分のものを使用した場合,接眼ミクロメーターの見え方は変化しないが,対物ミクロメータ―は小さく見えるため,③が解答になる。
問3
(1)
外膜,内膜,チラコイド,グラナ,ストロマの用語は押さえておきたい。杏林大学2023年にミトコンドリアの各場所も聞かれているので,そのあたりも確認しておくと良いでしょう。
(2)
光化学系Ⅰと光化学系Ⅱは,チラコイド膜上に存在する。
カルビン回路は,ストロマの起きる反応である。
(3)
チラコイド膜内腔からストロマに移動する際に,ATPが合成される。
(4)
グルコース:5.6/22.4×1/6×180=7.5
O2:酸素の物質量と二酸化炭素と等しいため,体積も等しい。
問4
(1) 交配結果を見ると,メス親の影響を受けていることがわかるため,③が選べる。
(2) 体細胞分裂の分裂中期であることから,DNA量は4になる。
(3) 交配結果の胚発生が「第1回目に体細胞分裂の分裂中期で停止」という結果から,「複製でできた2本の染色体の分離」が選べる。
(4) Aa×Aaの交配結果は,AA:Aa:aa=1:2:1である。よって,25%である。
Ⅲ
問1 ③
活動電位が発生する前の静止電位の値を答えればよいので,-60mVである。
問2 ③
図2の時間tにおいて,活動電位が生じている状態なのでNa+が流入している図を選びたい。
問3 ②
刺激源が図の左側にあるため,伝導は左から右に流れるため,②が選べる。
問4 ③
Na+の濃度を3分の1に減少させたら,Na+に流入量が減少するため,活動電位の最大値が減少する。
問5 ②
シナプス後膜で開口しているのは,神経伝達物質(リガンド)依存性イオンチャネルであるため,そもそも電位依存性ではない。また,活動電位が生じているので,Na+である。
問6 ②
空間的加重の選択肢である②を選べばよい。ただ,時間的加重に見える①の選択肢は,1秒間で2回は間隔が横軸と比べ空きすぎているので不適切である。
Ⅳ
問1
(1)
1本のポリペプチドから構成されるタンパク質の立体構造なので、αらせん(ヘリックス)構造、βシート構造からなり、不規則なペプチド結合したものは三次構造である。
四次構造は三次構造が集まった立体構造である。
(2)
二次構造は水素結合で形づくられている。三次構造はシステインというアミノ酸によるS-S結合(ジスルフィド結合)により形づくられている
(3)
平行に並んだ3つの矢印による板状の構造はβシート構造である
ちなみに選択肢②のシャペロンはタンパク質を規則正しく折り畳むためのタンパク質である。
問2
(1)
阻害薬は基質Sとよく似た立体構造を持っているので,競争的阻害である。阻害薬が酵素の活性部位に結合することで,酵素と基質が結合することを妨げている。
(2)
反応速度において,競争的阻害では基質濃度が低い時は阻害剤の影響は大きいが,基質濃度が高い時は阻害剤の影響はほとんどない。基質が十分量あるので,Vmaxは変化しない。
しかし最大反応速度の2分の1となるときであるKmの場合は基質濃度を高くしないといけないため,Kmの値は大きくなる。
(3)
阻害薬Dは低い濃度で酵素の働きを2分の1にできるため,効果的に細胞の増殖を抑制することができる。
(4)
ヒトに対する抗菌薬として考える。
阻害薬Dでは細菌の増殖抑制効果が高いが,哺乳類(ヒト)のタンパク質の阻害も大きくなってしまっている。
阻害薬Bでは哺乳類(ヒト)のタンパク質の阻害をあまりしていないが,細菌の増殖抑制効果も大きい。よって細菌とタンパク質の阻害と哺乳類のタンパク質の阻害の割合を比べた場合に,阻害薬Bの方が適していると考えられる。
入試直前講習のお知らせ
プラタナスでは今年の私立医学部受験生に対して入試直前講習を行なっております。
参加費は無料!定員は15名です。詳しくはこちら。
医学部専門予備校プラタナスへのお問い合わせ
その他入塾やご質問事項に関しては。「お問い合わせ」または「LINE無料相談」からお気軽にご連絡ください。
面談はリモートでも受け付けております。

無料LINE相談
随時受付中
無料
体験・相談
お申し込み


 アクセス
アクセス
