解答速報/入試分析
2025年1月29日
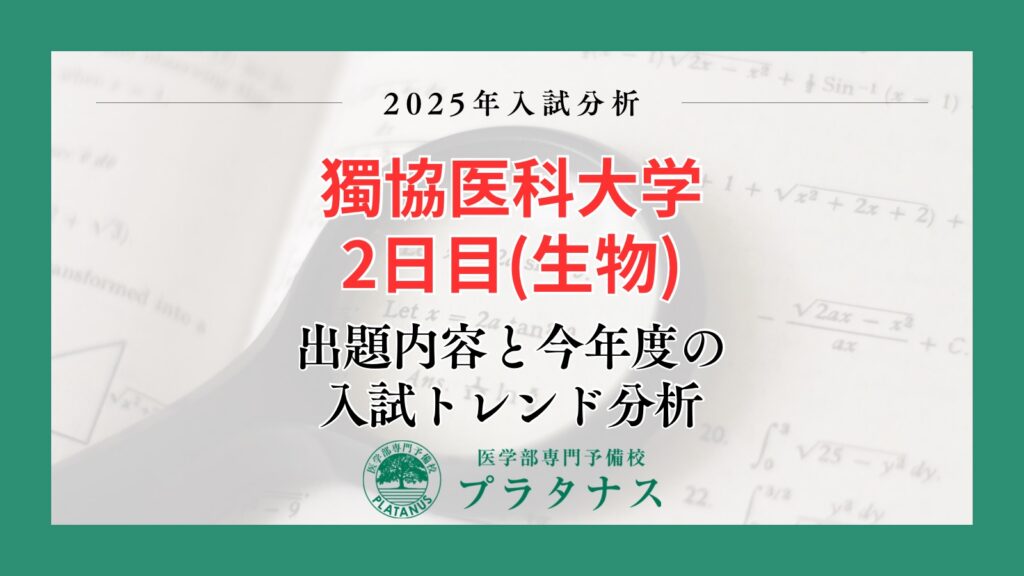
私立医学部専門予備校のプラタナスです。
獨協医科2日目
試験の結果も出始めてきており,結果がでないときは苦しい気持ちになりますが、勉強することでしか合格の可能性は広げられません。日々試験でできなかったところを復習し,明日の試験に向けて挑んでいきましょう。合格の吉報を勝ち取るまで,ひたすら続けていくことで光が見えます。獨協医科2日目で特徴的だった「呼吸商の実験」,「自家不和合性」,「物質生産」についてまとめます。
呼吸(呼吸商の実験)
呼吸商(RQ)は放出される二酸化炭素量÷吸収される酸素量
で求められる。
それぞれの呼吸基質の呼吸商の値は決まっており,
炭水化物は1.0,タンパク質は0.8,脂肪は約0.7となっている。
呼吸商の測定実験ではフラスコ内(フラスコAとフラスコBとする)に発芽種子を入れ,フラスコAにKOH(水酸化カルシウム),フラスコBにKOHと同体積の水を入れて,フラスコ内の体積の増減から呼吸商を測定する。
このとき,KOHは二酸化炭素吸収剤として作用しており,フラスコAは吸収された酸素の量。フラスコBは吸収された酸素の量と排出した二酸化炭素の量の差を表す。
RQを求めるときは(フラスコAの体積の減少量-フラスコBの体積の減少量)÷(フラスコAの体積の減少量)で求められる。
この結果からコムギは炭水化物,ダイズはタンパク質,トウゴマは脂肪を呼吸基質として利用していることが分かる。
他には草食動物であるウシは0.96,雑食であるヒトは0.89,肉食であるネコは0.74くらいになる。
自家不和合性
植物には他の個体と交配をするために,自家受精を避けるしくみをもつものがある。
自身の花粉と受粉しても受精に至らないしくみがあり,これを自家不和合性という。
例えばナス科,バラ科の植物では,花粉がS1型(雄性因子),花柱がS2型とS3型の場合(S2S3は雌性因子),花粉管が伸長し受精可能となり,S1S2型の受精卵か,S1S3型の受精卵を作ることが可能である。一方,花粉がS3型(雄性因子),花柱がS2型とS3型の場合(S2S3は雌性因子),花粉管が伸長できないため,受精は不可能となる。
またアブラナ科の場合はしくみはやや異なるため,問題文を読み取ることが大事である。
遺伝の問題を絡めて出題されることが多い。
物質生産
①純生産量=総生産量-呼吸量
(純生産量=成長量+被食量+枯死量)
②摂食量=被食量
③同化量=摂食量-不消化排出量
④生産量=同化量-呼吸量
(生産量=成長量+被食量+死滅量)
以上の式がなかなか覚えられない受験生もいると思います。
①は植物の式,②は植物と動物をつなぐ式,③と④は動物の式と考えてみましょう。
また純生産量と生産量はイメージ的にはほぼ同じで,植物の総生産量は動物の同化量と同じと考えると,覚えることが少なくて済みます。
特徴としては③で「不消化排出量」は動物にしかありません。①と④は式的にはほぼ同義です。
・純生産量が大きい生態系
単位面積当たりの純生産量が大きい生態系は,海洋ではサンゴ礁や藻類の茂み,陸上では亜熱帯多雨林などがある。生物の種数や生物量が大きい。
・森林の純生産量の割合
地球表面の15%を占める森林の純生産量は,地球全体の50%にもなる。また低緯度(赤道付近)の森林ほど,単位面積あたりの純生産量は大きい。これは気候が光合成に適するためである。ちなみに海洋の物質生産は高緯度地域でも大きいところもある。
・森林の純生産量の比較
熱帯多雨林と照葉樹林を比較してみる。
熱帯多雨林は1年を通して光合成が盛んに行われるため,総生産量は大きい。
しかし呼吸量も大きいので,純生産量は比較的小さい。一方,照葉樹林は呼吸量が比較的小さいため,純生産量の割合が大きい。
・エネルギー効率
生産者のエネルギー効率=総生産量÷太陽の入射エネルギー量×100
消費者のエネルギー効率=その栄養段階の同化量÷前の段階の同化量(または総生産量)×100
で求めることができる。
一般的に生産者のエネルギー効率は低く,栄養段階が高次の消費者になるほどエネルギー効率は上がる。
入試直前講習のお知らせ
プラタナスでは今年の私立医学部受験生に対して入試直前講習を行なっております。
参加費は無料!定員は15名です。詳しくはこちら。
医学部専門予備校プラタナスへのお問い合わせ
その他入塾やご質問事項に関しては。「お問い合わせ」または「LINE無料相談」からお気軽にご連絡ください。
面談はリモートでも受け付けております。

無料LINE相談
随時受付中
無料
体験・相談
お申し込み


 アクセス
アクセス
