解答速報/入試分析
2025年1月29日
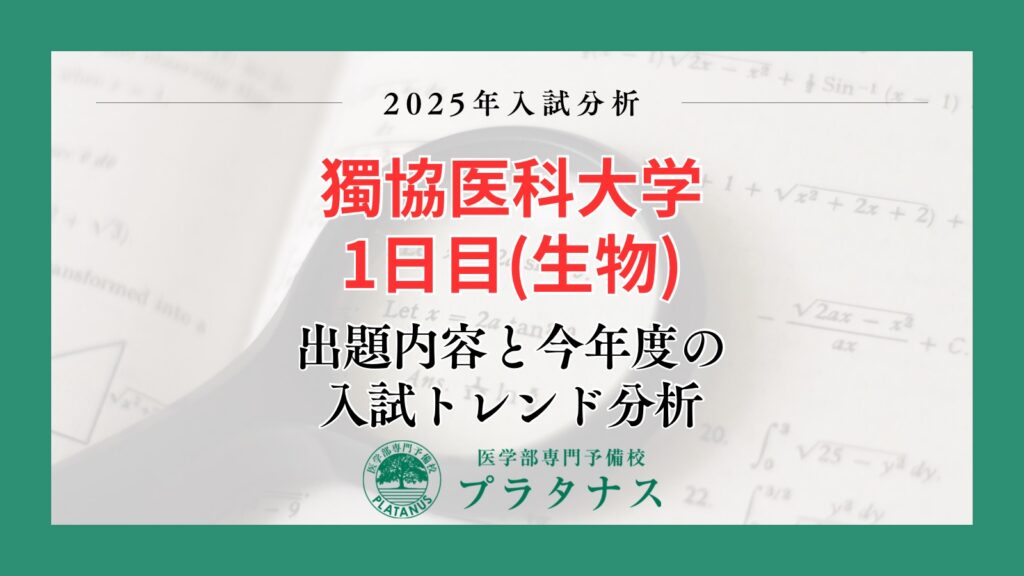
私立医学部専門予備校のプラタナスです。
獨協医科大学の試験お疲れ様でした。
獨協医科1日目では幅広い範囲から出題されていましたので,金沢医科に向けて確認となれば幸いです。金沢医科大学でも幅広い単元から出題されるので,弱点分野などの確認となります。
細胞膜について
・細胞膜の厚さは5nm~10nmくらいである。
他に大きさでおさえておくべきものは,
ゾウリムシ(180μm~300μm),ヒトの卵(140μm),ヒトの精子(60μm),赤血球(7~8μm),葉緑体(5μm),大腸菌(3μm),ミトコンドリア(2μm),ウィルス(100nm)。
・細胞膜の水の透過性
水は極性分子であり,単純拡散による細胞膜の透過速度は酸素や二酸化炭素に比べるとかなり小さい。なので水を特異的に透過させるアクアポリン(水チャネル)が存在する。
光合成
・チラコイド膜での反応
光エネルギーがチラコイド膜上にある光化学系Ⅰ・Ⅱにあたりe-を放出する。
光化学系Ⅱでは水が分解され,酸素が発生する。e-は光化学系Ⅱに渡される。
光化学系Ⅱから光化学系Ⅰへ電子が移動するときのエネルギーを用いて,H+をストロマ側からチラコイド内腔へ能動輸送する。チラコイド内腔のH+が高濃度になるとATP合成酵素を通ってATPを産生する。光化学系Ⅰのe-はNADP+とH+からNADPH+H+を生成。
・ストロマでの反応
チラコイド膜で生じたATPとNADPH+H+を用いて,カルビン回路で二酸化炭素を還元して有機物を作る。二酸化炭素1分子とRuBP(リブロース二リン酸)からPGA(ホスホグリセリン酸)2分子をつくり出す酵素は,ルビスコとよばれる。
ATPはPGAからGAP(グリセルアルデヒドリン酸)になるときと,有機物を作ってからRuBPになるときに消費される。
・光合成曲線から増加した有機物量を求める場合は,見かけの光合成速度を見て,
有機物の量をxとおくと
180:6×44=x:見かけの光合成速度
で比例式を用いて計算していく。
・ペーパークロマトグラフィーの実験
光合成色素を分離する実験として,ペーパークロマトグラフィーの実験がある。
葉をすりつぶし,有機溶媒(ジエチルエーテルなど)に溶かす。
そしてその溶液を原点において展開させる。展開の先端を溶媒前線といい,
展開の先端から,カロテン→キサントフィル→クロロフィルa→クロロフィルbの順に展開していく。
原点から溶媒前線までの距離を分母,原点から各色素の先端までの長さを分子とした値はRf値といい,Rf値はカロテン>キサントフィル>クロロフィルa>クロロフィルbの順になる。
減数分裂
卵の配偶子形成は,始原生殖細胞(2n)→卵原細胞(2n)→(成長)→一次卵母細胞(2n)→二次卵母細胞(2n)と一次極体(2n)→卵細胞(n)と極体3つができる。
ゆえに,卵細胞が10コあった場合は極体は30コできる計算になる。
ショウジョウバエの分節遺伝子
・ショウジョウバエの前後軸は母性因子により決定され,前部はビコイド遺伝子が発現し,後部はナノス遺伝子が発現する。それぞれが位置情報となって前後で異なる遺伝子が発現する。
・分節遺伝子
ギャップ遺伝子(前後軸にそって発現し,からだを大まかな領域で分ける)
ペアルール遺伝子(7本の縞模様ができ,体節のもとになる構造をつくる)
セグメントポラリティ遺伝子(14本の縞状に発現し,体節中の前後の決定をする)
その後ホメオティック遺伝子により,それぞれの体節で器官が形成される。
・神経誘導
外胚葉表面はなにも作用を受けなければ神経に分化する。
BMP(骨形成因子)が外胚葉表面の受容体に結合すると表皮に分化するが,原口背唇部(脊索)から分泌されるノギンやコーディンというタンパク質はBMPと結合し,BMPが外胚葉表面と結合するのを阻害する。よってその領域は神経へと分化する。
補酵素について
セロハンを用いた透析実験が有名
補酵素の性質は
・酵素本体と容易に着脱する
・熱に強い
・低分子化合物
という特徴がある。
アポ酵素と補酵素が結合した状態をホロ酵素といい,ホロ酵素は酵素活性を示す。
神経系
神経系は大きく中枢神経(脳と脊髄)と末梢神経(脳神経・脊髄神経)に分かれる。
末梢神経は体性神経系と自律神経系に分かれる。さらに体性神経系は感覚神経と運動神経にわかれる。自律神経系は交感神経と副交感神経にわかれる。
脳や脊髄において灰白質に見えるのはニューロンの細胞体が密集し,白質に見えるのはニューロンの神経繊維が集まっているからである。
脳では外側(皮質)が灰白質,脊髄では内側(髄質)が灰白質となっている。
受容器からの刺激は感覚神経を通り,延髄で交差し大脳へと伝わる。
・反射について
大脳を経由しない素早い反応を反射といい,その経路のことを反射弓という。
反射の中枢となるのは,中脳(動眼・瞳孔反射),延髄(せき・くしゃみ・だ液の分泌),脊髄反射がある。脊髄反射の例として,膝蓋腱反射(ひざの上を叩くと足が跳ね上がる)と屈筋反射(熱いものに触れると手を引っ込める)がある。
バイオーム
・世界のバイオーム
熱帯・亜熱帯多雨林→発達した階層構造があり,つる性植物が多い。ヘゴ,ビロウ,ガジュマル,ソテツ
照葉樹林→乾季がほとんどない地域に発達。シイ,カシ,タブノキ,クスノキ,ヤブツバキ
夏緑樹林→冬期に落葉。ブナ,ミズナラ,カエデ
針葉樹林→葉が細長い。エゾマツ,トドマツ,トウヒ,シラビソ,コメツガ
硬葉樹林→地中海性気候(夏は乾燥,冬は湿潤)。オリーブ,コルクがし,ゲッケイジュ
雨緑樹林→乾季に落葉。チーク,コクタン
サバンナ→木が点在,イネ科の草本が主体
ステップ→木がない,イネ科の草本が主体
砂漠→多肉植物,サボテン,ベンケイソウ
ツンドラ→地衣類,コケ類
・日本の垂直分布
日本は世界的にみて降水量が十分あるので,年平均気温によってバイオームが異なる。
100m高さが上昇するごとに-0.5℃となる。
中部地方の山では海抜0m~700mまでを丘陵帯(照葉樹林が中心),700m~1700mまでを山地帯(夏緑樹林が中心),1700m~2500mまでを亜高山帯(針葉樹林が中心),2500m以上を高山帯(高山植物)という。
入試直前講習のお知らせ
プラタナスでは今年の私立医学部受験生に対して入試直前講習を行なっております。
参加費は無料!定員は15名です。詳しくはこちら。
医学部専門予備校プラタナスへのお問い合わせ
その他入塾やご質問事項に関しては。「お問い合わせ」または「LINE無料相談」からお気軽にご連絡ください。
面談はリモートでも受け付けております。

無料LINE相談
随時受付中
無料
体験・相談
お申し込み


 アクセス
アクセス
